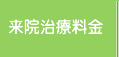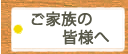2014年11月26日
時間医学 その③ …こころの時計
こんにちは。くすのき鍼灸院 渡邉です。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
についての第三回目になります。
時間医学 その③ …こころの時計

皆さんは子供のころより今の方が時間が経つのが早く感じませんか?
子供のころは気の済むまで遊んだころ、夕焼けになったような記憶があります。
今は午前中はもちろん、夕方になるのがあっという間。
一日、一週間、一ヶ月… 一年さえあっという間の感があります。
これは「実際の時間」と「こころの時間」に違いがあるからです。
大塚先生はこんなことをおっしゃっていました。
・10歳の一年は人生の10分の1の時間
・70歳の一年は人生の70分の1の時間
「こころの時計」に影響を与える要因は、様々な実験研究から分かってきている様です。
代謝
代謝が良いほど、心の時計が早く進み、時間を長く感じる。年とともに時間の経過を早く感じるのは、代謝が落ちるから、とも説明できる。
感情
恐怖を伴う時間は長く感じるらしい。
時間に注意を向ける頻度
頻繁に時計を気にすると、長く感じる。つまらない時間は、時間に注意が向きやすいので長く、逆に何かに集中すると短い。
印象に残る出来事の数
印象に残る出来事が多い時間の方が、長く感じられる傾向がある。
刺激
大きい物・音に接するなど、強い刺激を受けた時間の方が長く感じる。
これらは仮説や研究段階のものが多いようですが、納得できるような気がします。
ではこの 「こころの時計」 はどこにあるのでしょう?
大脳の「島皮質」にあります。

島皮質(とうひしつ、英: insular cortex)は大脳皮質の一領域。
脳葉のひとつとして島葉と呼ばれたり、脳回の一つとして島回と呼ばれたり、単に島とも呼ばれています。

島皮質は機能的に前部と後部に分かれており、
島皮質前部は嗅覚、味覚、内臓自律系、及び辺縁系の機能により強く関わり、
島皮質後部は聴覚、体性 感覚、骨格運動とより強く関わっています。
Wikipediaより
また、島皮質は痛みの体験や喜怒哀楽や不快感、恐怖などの基礎的な感情の体験に重要な役割を持つことが示されています。
つまり 「島皮質は感情や自己認識に強く関与している」 ことになり、
感情・自己認識 = 「こころ」と考えてよいと思うので、
島皮質で 「こころの時計」 が形成されていると言える様です。
本来の島皮質の能力は、危機に直面した時に逃げるか戦うかを瞬時に判断するものであったようです。
しかし人間はこの能力を進化させ、怒りや悲しみ、思いやりまで感じるようになり、操れるようになった。
こころの時計を身につけたおかげで、今日まで発展出来たともいえ、人間にとってとても重要な能力だと言えます。
認知機能についてのお話もありました。
「こころの時計」 はいろいろな面を持ち合わせているとの事ですが、日常行動から複雑な精神活動まで、ほとんどの高次脳機能の活動に、時間認知の関与が推察されているそうです。
そこで、3年後の認知機能を予測する要因として、10秒の時間予測が、統計上有意を示す要因として抽出されたそうです。

簡単に言うと、今後(3年後)の認知機能の程度を知りたいと思っている方に、10秒数えてもらい、どれほど正確な10秒と離れているかを調べます。
離れれば離れるほど3年後の認知機能の低下が予測できると言うことです。
逆に、10秒の時間予測を訓練することにより、認知機能を改善させることが出来るとの事でした。
とても興味深いお話でした。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
についての第三回目になります。
時間医学 その③ …こころの時計

皆さんは子供のころより今の方が時間が経つのが早く感じませんか?
子供のころは気の済むまで遊んだころ、夕焼けになったような記憶があります。
今は午前中はもちろん、夕方になるのがあっという間。
一日、一週間、一ヶ月… 一年さえあっという間の感があります。
これは「実際の時間」と「こころの時間」に違いがあるからです。
大塚先生はこんなことをおっしゃっていました。
・10歳の一年は人生の10分の1の時間
・70歳の一年は人生の70分の1の時間
「こころの時計」に影響を与える要因は、様々な実験研究から分かってきている様です。
代謝
代謝が良いほど、心の時計が早く進み、時間を長く感じる。年とともに時間の経過を早く感じるのは、代謝が落ちるから、とも説明できる。
感情
恐怖を伴う時間は長く感じるらしい。
時間に注意を向ける頻度
頻繁に時計を気にすると、長く感じる。つまらない時間は、時間に注意が向きやすいので長く、逆に何かに集中すると短い。
印象に残る出来事の数
印象に残る出来事が多い時間の方が、長く感じられる傾向がある。
刺激
大きい物・音に接するなど、強い刺激を受けた時間の方が長く感じる。
これらは仮説や研究段階のものが多いようですが、納得できるような気がします。
ではこの 「こころの時計」 はどこにあるのでしょう?
大脳の「島皮質」にあります。

島皮質(とうひしつ、英: insular cortex)は大脳皮質の一領域。
脳葉のひとつとして島葉と呼ばれたり、脳回の一つとして島回と呼ばれたり、単に島とも呼ばれています。

島皮質は機能的に前部と後部に分かれており、
島皮質前部は嗅覚、味覚、内臓自律系、及び辺縁系の機能により強く関わり、
島皮質後部は聴覚、体性 感覚、骨格運動とより強く関わっています。
Wikipediaより
また、島皮質は痛みの体験や喜怒哀楽や不快感、恐怖などの基礎的な感情の体験に重要な役割を持つことが示されています。
つまり 「島皮質は感情や自己認識に強く関与している」 ことになり、
感情・自己認識 = 「こころ」と考えてよいと思うので、
島皮質で 「こころの時計」 が形成されていると言える様です。
本来の島皮質の能力は、危機に直面した時に逃げるか戦うかを瞬時に判断するものであったようです。
しかし人間はこの能力を進化させ、怒りや悲しみ、思いやりまで感じるようになり、操れるようになった。
こころの時計を身につけたおかげで、今日まで発展出来たともいえ、人間にとってとても重要な能力だと言えます。
認知機能についてのお話もありました。
「こころの時計」 はいろいろな面を持ち合わせているとの事ですが、日常行動から複雑な精神活動まで、ほとんどの高次脳機能の活動に、時間認知の関与が推察されているそうです。
そこで、3年後の認知機能を予測する要因として、10秒の時間予測が、統計上有意を示す要因として抽出されたそうです。

簡単に言うと、今後(3年後)の認知機能の程度を知りたいと思っている方に、10秒数えてもらい、どれほど正確な10秒と離れているかを調べます。
離れれば離れるほど3年後の認知機能の低下が予測できると言うことです。
逆に、10秒の時間予測を訓練することにより、認知機能を改善させることが出来るとの事でした。
とても興味深いお話でした。
2014年11月18日
時間医学 その② …腹時計
こんばんは。くすのき鍼灸院 渡邉です。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
についての第二回目になります。
時間医学 その② …腹時計
時間栄養学から
大塚先生によると、身体を守るには3つの時計が必要との事。
①体内時計 ②腹時計 ③こころの時計 です。
そのうちの ②腹時計 のお話です。

食事は人間が健康な生活を送るにために重要な役割を持っています。
体内時計は消化器系の臓器にももちろんあります(腹時計)。
この腹時計を有効に活用するためには 「朝の光」 と 「朝食」 が大切になります。
体内時計を規則正しい24時間周期にするためには、1日1回、時間合わせをする必要があり、その目安となるのが
脳の時計遺伝子を動かす「朝の光」と
内臓の時計遺伝子を動かす「朝食」なのです。
・朝食を摂らないと太る。
・朝、炭水化物を多く摂ると、その後は少なくなる。
・夜食は太る
とおっしゃっていました。
この中の「夜食は太る」という項目
…気になりますよね~(笑)
キーワードは、「 BMAL1(ビーマルワン) 」。
BMAL1(ビーマルワン)は、細胞の中にあるタンパク質で、体内に脂肪分を取り込む働きがあります。
しかもBMAL1(ビーマルワン)は時間によって数が変わり、
朝の6時から急激に減り始め、
昼の3時にもっとも分泌量が少なくなります。その後は分泌量が増えていき、
夜の10時から夜中の2時にかけて、分泌量が最大になるという特徴があります。
夜10時~深夜2時はまさに「魔の時間帯」です
&「3時のおやつ」は最も脂肪になりにくい …昔の人の経験からの知恵はすばらしいです

他の方の研究では、朝食を抜くと、脳にエネルギー源の糖質が送られず、「糖新生反応」が起こり、
筋肉を壊して糖をつくるため、筋肉が落ち、基礎代謝も落ちてしまうとの事。
朝食欠食者は摂食者の5倍肥満になりやすいというデータもあるそうです
朝食に糖質やたんぱく質を摂取すると、代謝が上がり、1日のエネルギー消費も大きくなります。
しっかり朝食を摂り、生活リズムを作ることが重要なのですね
次回は、「こころの時間」です。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
についての第二回目になります。
時間医学 その② …腹時計
時間栄養学から
大塚先生によると、身体を守るには3つの時計が必要との事。
①体内時計 ②腹時計 ③こころの時計 です。
そのうちの ②腹時計 のお話です。

食事は人間が健康な生活を送るにために重要な役割を持っています。
体内時計は消化器系の臓器にももちろんあります(腹時計)。
この腹時計を有効に活用するためには 「朝の光」 と 「朝食」 が大切になります。
体内時計を規則正しい24時間周期にするためには、1日1回、時間合わせをする必要があり、その目安となるのが
脳の時計遺伝子を動かす「朝の光」と
内臓の時計遺伝子を動かす「朝食」なのです。
・朝食を摂らないと太る。
・朝、炭水化物を多く摂ると、その後は少なくなる。
・夜食は太る
とおっしゃっていました。
この中の「夜食は太る」という項目
…気になりますよね~(笑)
キーワードは、「 BMAL1(ビーマルワン) 」。
BMAL1(ビーマルワン)は、細胞の中にあるタンパク質で、体内に脂肪分を取り込む働きがあります。
しかもBMAL1(ビーマルワン)は時間によって数が変わり、
朝の6時から急激に減り始め、
昼の3時にもっとも分泌量が少なくなります。その後は分泌量が増えていき、
夜の10時から夜中の2時にかけて、分泌量が最大になるという特徴があります。
夜10時~深夜2時はまさに「魔の時間帯」です

&「3時のおやつ」は最も脂肪になりにくい …昔の人の経験からの知恵はすばらしいです


他の方の研究では、朝食を抜くと、脳にエネルギー源の糖質が送られず、「糖新生反応」が起こり、
筋肉を壊して糖をつくるため、筋肉が落ち、基礎代謝も落ちてしまうとの事。
朝食欠食者は摂食者の5倍肥満になりやすいというデータもあるそうです

朝食に糖質やたんぱく質を摂取すると、代謝が上がり、1日のエネルギー消費も大きくなります。
しっかり朝食を摂り、生活リズムを作ることが重要なのですね

次回は、「こころの時間」です。
2014年11月13日
時間医学 その①
こんにちは。くすのき鍼灸院 渡邉です。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
について書いていきます。
時間医学 その①
時間医学とは…

時間医学とは「時間生物学」という生物の生体リズムを研究する学問の考え方を、医学分野に取り入れたものです。
生活習慣病から老化・発癌まで、健康を脅かす病態と時計機構(時計遺伝子)との関わりが認識されているそうです。
たとえば、時計遺伝子に異常があると生体リズムが乱れ、肥満・高血圧・糖尿病が発生し、抑うつ気分が現れ、癌にもなってしまうとの事。

体内時計はどこにある?
最初、脳内の視床下部の視交叉上核に体内時計があることが発見されました。
その後、その中に時を刻む時計遺伝子があることも発見。
さらに、心臓やその他臓器、血管をはじめ身体のすみずみ、ほとんどの細胞に時計遺伝子が見つかり、脳が親時計、そのほかは子時計として連動していることもわかりました。

親時計は子時計を指揮し、地球の自転に合わせた約24時間のリズム(サーカディアンリズム)を刻んでいるのです。
なぜこのリズムを刻んでいるかというと、私たちが地球で生きていくために、その時間を知り、利用する必要があるからです。

この考え方は「クロノミクス」といい、生命と環境との相互の力学を研究する学問でもあるそうです。
今回は、
第40回現代医療鍼灸臨床研究会の特別講演
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」(東京女子医科大学名誉教授 大塚邦明先生)
について書いていきます。
時間医学 その①
時間医学とは…

時間医学とは「時間生物学」という生物の生体リズムを研究する学問の考え方を、医学分野に取り入れたものです。
生活習慣病から老化・発癌まで、健康を脅かす病態と時計機構(時計遺伝子)との関わりが認識されているそうです。
たとえば、時計遺伝子に異常があると生体リズムが乱れ、肥満・高血圧・糖尿病が発生し、抑うつ気分が現れ、癌にもなってしまうとの事。

体内時計はどこにある?
最初、脳内の視床下部の視交叉上核に体内時計があることが発見されました。
その後、その中に時を刻む時計遺伝子があることも発見。
さらに、心臓やその他臓器、血管をはじめ身体のすみずみ、ほとんどの細胞に時計遺伝子が見つかり、脳が親時計、そのほかは子時計として連動していることもわかりました。

親時計は子時計を指揮し、地球の自転に合わせた約24時間のリズム(サーカディアンリズム)を刻んでいるのです。
なぜこのリズムを刻んでいるかというと、私たちが地球で生きていくために、その時間を知り、利用する必要があるからです。

この考え方は「クロノミクス」といい、生命と環境との相互の力学を研究する学問でもあるそうです。
2014年11月08日
現代医療 40回記念大会
こんにちは。くすのき鍼灸院 渡邉 です。
11/3(月曜)文化の日に東京大学で行われる「現代医療鍼灸臨床研究会」に出席してきました。

研究会のテーマは、通常ではひとつの疾患に絞って医大の教授の講演や、鍼灸師の先生方たちによる研究や臨床の発表を行いますが、
今回は40回記念大会で、テーマは「これからの医療に求められる鍼灸」でした。
今回その中でも、
東京女子医大名誉教授の大塚邦明先生による
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」や
昭和大学准教授の砂川正隆先生による
「疼痛ならびにストレスに対する針治療の新知見」、
埼玉精神神経センターセンター長の丸木雄一先生の
「難病を中心とした医療連携」
がとても興味深く、印象深かったです。

東大医学部本館
次回から、このブログでもそれぞれの講演の内容を少しですが書いていきたいと思います。
11/3(月曜)文化の日に東京大学で行われる「現代医療鍼灸臨床研究会」に出席してきました。

研究会のテーマは、通常ではひとつの疾患に絞って医大の教授の講演や、鍼灸師の先生方たちによる研究や臨床の発表を行いますが、
今回は40回記念大会で、テーマは「これからの医療に求められる鍼灸」でした。
今回その中でも、
東京女子医大名誉教授の大塚邦明先生による
「時間医学(体内時計)の臨床への応用」や
昭和大学准教授の砂川正隆先生による
「疼痛ならびにストレスに対する針治療の新知見」、
埼玉精神神経センターセンター長の丸木雄一先生の
「難病を中心とした医療連携」
がとても興味深く、印象深かったです。

東大医学部本館
次回から、このブログでもそれぞれの講演の内容を少しですが書いていきたいと思います。